先日、実業家の堀江貴文さんが出資している宇宙ベンチャー:インターステラテクノロジズの2号機ロケットが失敗したときに知人から
「ロケットの打ち上げ失敗ってこんなもんでしょうか?」と質問がありました。
ロケットの開発では基本設計→詳細設計、そしてプロトタイプモデルなど何段階かの開発品フェーズを得て実際に使用までもっていくんですが、それぞれの段階で有識者によるレビューが必ずあります。
新しい、若い開発者が気がつかないようなところを知識と経験のある技術者の目からその設計が問題ないかを確認を。そんな関門を経て、仕様が決まったら開発品はロケットの使用環境に耐えられる、宇宙空間に耐えられるさまざまな試験を行います。
ロケットのエンジンだと
燃料となる液体や気体が漏れないかを確認する”漏洩(リーク)試験”
エンジン部品がロケット飛翔時の振動に問題なく動くかと確認する”振動試験”
そして、実際に開発したエンジンが正しく燃えるか、燃えている時に異常に温度上昇している箇所がないかなどを確認する”燃焼試験”があります。
メインの試験はこの”燃焼試験”です。一番試験費用かかりますが、実際のものとほどんど同じものをで燃焼させますので、模擬試験では得られないリアルな結果が得られるので重要です。

今回もこういう流れは踏んでいるのかもですが、少し開発ステップの仕方や今までの知見などの点が弱いのかもしれません。
確かに宇宙開発に限らず、開発時には失敗はつきもの(というか失敗の数のほうが多いはず)なんですが、液体燃料を使ったもっと大型のロケット H2AなどはJAXA、三菱が開発し、何十回も打ち上げし、安定して成功しています。ロケットの大きさや使っている液体燃料の種類の違いはあれ、技術的に共通している部分は多いはず。
なので、JAXAやロケットメーカーが持っている技術を共有して、なるべく打ち上げ失敗となるリスクを減らしていくことはできるのではないかと思っています。それぞれが持っている固有の技術を秘密を守ると言うことも大切なことだと思うのですが、世界で宇宙開発で遅れをとっている日本では、そんなことは言っていられないのが現実でじゃないかなと感じています。
アメリカの宇宙ベンチャーとして既存メーカーをおびやかす存在となった”スペースX”もボーイングなどの優秀な技術者を引っ張って、今までではありえないスピードでロケット開発をして成功してきました。(最近、イーロンマスクの本を読んでそのことがよくわかりました。もちろん開発の段階で失敗も多く経験しているのも事実です。)
宇宙ベンチャーでロケット技術のキャリアがある元開発者などを雇用するのは資金面でもなかなか厳しい事情もあるなら、オールジャパンで協力して、これからニーズが高まる小型ロケット打ち上げ競争に立ち向かっていく必要があると思います。
宇宙ちゃんねるも宇宙ベンチャーの事情をきいてみて、何かできることがあればやっていこうと。自分の目指すところ:”日本を宇宙先進国に”の一歩になればと思います。


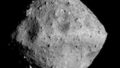

コメント